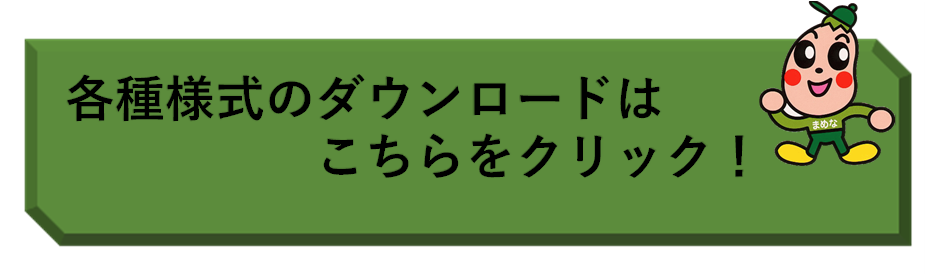更新状況
(R6.11.29)実施要綱の一部を改正しました。
・令和6年12月2日をもって現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、助成に係る事務における医療保険の加入関係の確認方法に関する規定を改めました。
・受給者証交付申請書等様式の一部を修正しました。
(R6.3.26)実施要綱の一部を改正しました。
・地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等が行われたことを踏まえ、自己負担限度額の決定に係る寡婦控除等のみなし適用に関する規定を削除しました。また、これに伴い、様式第13号を削除しました。
・償還払申請書(様式第10号)を全面改正しました。
・受給者証交付申請書(様式第1号)を一部改正しました。
(R6.2.20)実施要綱の一部を改正しました。
●他の都道府県に転出した受給者が転出前に本県から交付されていた受給者証の有効期間の終期までに本県に再び転入したときは、当該受給者が転入元の都道府県で受給者証の交付を受けていない場合に限り、新規申請の扱いとせず、転入日から転出前の受給者証の有効期間の終期までの受給者証の交付を受けることができるものとしました。
また、これに伴い、様式第9号を一部変更しました。
1.制度の概要
☆島根県肝炎治療医療費助成事業実施要綱(令和6年11月29日改正)(303KB)
◆B型及びC型ウイルス性肝炎の治療を受ける際に治療に要した医療費を助成します。
◆対象となるのは次の1から4の要件を全て満たす方となります。
-
島根県に住民票上の住所を有する方
-
医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
-
対象の医療について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われていない方
-
本制度の利用を申請し、島根県の審査により認定された方
月に一度開催する専門医による認定審査会で受給資格が認められれば、受給者証が発行され、
自己負担限度額を超える部分について医療費の助成を受けることができます。
※制度利用にあたっては、お住まいの地域を管轄する保健所への申請が必要です。
2.助成対象となる医療
-
B型及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用となっているもの
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロンフリー治療で、保険適用となっているもの
-
B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの
-
1~3の治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料及び薬剤料
(肝炎の治療と無関係の治療や入院時の食事療養費及び生活療養費は助成の対象外となります) -
当該治療の中断を防止するために併用して行う副作用の治療
3.助成を受けられる期間
-
1年以内で治療予定期間に即した期間となります。
- 核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続が必要と認める場合、1年毎の更新を行うことができます。
-
助成期間の始期は、受給者証交付申請書を保健所が受理した月の初日となります
-
よって、治療を開始される場合の検査日や治療開始日の決定に当たっては、この点に留意して医師と十分にご相談ください。
※インターフェロン治療については、2回目の制度利用が可能な場合があります。
また、例外的に期間を延長できる場合があります。(期間延長の取扱[PDF/106.0KB])
4.医療費の自己負担限度額
| 階層区分 |
自己負担限度額 (月額) |
|
|---|---|---|
| 甲 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
| 乙 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
※「世帯」については、住民票上の世帯を単位とします。
しかし、配偶者以外の者であって、制度利用者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、
受給者からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税年額の合算対象から除外することを認める場合があります。
市町村民税額合算除外希望申請書(様式第12号)【PDF/72KB】【word/29KB】
※また、平成22年度税制改正における年少扶養控除等の廃止の影響を、制度利用者からの申請に基づき除外することができます。
5.受給者証の交付申請
| 名称 | 新規申請 |
更新申請 (核酸アナログ製剤治療のみ) |
|---|---|---|
| 1肝炎治療受給者証交付申請書 | ○ | ○ |
| 2主治医による診断書※1 | ○ | ○※2 |
| 3世帯全員の住民票 | ○ | ○ |
| 4住民票に記載されている方全員の市町村民税課税証明書※3 | ○※4 | ○※4 |
| 5制度利用希望者の医療保険の加入状況が確認できるもののコピー | ○ | ○ |
| 6受給者証のコピー | ○ | |
| ☆下記の書類は希望者のみ提出してください(新規・更新共通) | ||
| 7市町村民税額合算対象除外希望申請書 | ||
|
8市町村民税額合算対象除外希望申請する者の医療保険の加入状況が 確認できるもののコピー |
※1治療内容によって診断書の作成ができる医師が限定されています。
詳しくはこちらをご覧ください⇒[診断書の作成について]
※2核酸アナログ製剤治療の更新申請の場合は、前回の更新時以降の検査結果とお薬手帳のコピーをもって診断書に替えることができます。
※3明らかに収入がないと判断できる方(義務教育の終了していない方、19歳未満の高校生で収入がない方)については課税証明書の省略が可能です。
※4自己負担限度額が月額20,000円でよい場合は課税証明書を省略してもかまいません。
(その場合、例え実際の課税額が235,000円未満であったとしても自己負担額は10,000円ではなく20,000円となります)
6.医療費助成の仕組み
- 肝炎治療受給者証の交付を受けた方は、委託医療機関・薬局の窓口へ提示してください(その他の受給者証等をお持ちの方は一緒に提示してください)。
- 1か月につき、自己負担限度額(上記4を参照)を超える部分については原則として現物給付とします。
〈例.自己負担限度額が10,000円の方が助成対象となる治療に12,000円かかった場合、受給者証を提示していれば窓口での支払いは10,000円となります〉
- 1か月につき複数の委託医療機関等を受診される場合は、自己負担上限額管理票(受給者証に添付)により自己負担限度額を管理してください。
※注)受給者証及び自己負担上限額管理票を提示されない場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
治療当日に受給者証の提示を忘れた場合は、一旦窓口で全額お支払いしていただいた後、「7.償還払請求」の手続きを行って頂くこととなります。
7.償還払請求
受給者証が交付されるまでに治療を受けた場合や受給者証を忘れて受診した場合など、事情により受給者証の提示ができず、自己負担限度額を超えて医療費の支払を行った場合は、償還払手続きを行うことで、後日相当する医療費の支給が受けられます。
(その月の医療費が高額療養費の支給対象となる場合については、その高額療養費相当額を除く額を支給します。)
償還払手続きを行う場合は、次の書類を居住地を管轄する保健所へ提出してください。
・肝炎治療費償還払請求書(様式第10号)【PDF/218KB】【word/62KB】
・請求者(受給者)の医療保険の加入状況が確認できるものの写し
・請求者(受給者)の肝炎治療受給者証の写し
・当該月において受診した全ての保険医療機関・薬局が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書
・高額療養費の現物給付を受けた場合は、限度額適用認定証の写し等
・口座振替申出書(様式)【PDF/91.2KB】【word/54KB】
※今までに支給を受けたことがあり、その後氏名・住所・振込口座情報に変更がない場合は不要
8.受給者証の記載内容変更等
・受給者証に記載された事項の変更(住所の変更、医療機関の変更など)
・受給者証を紛失してしまった場合
・県外に転出する場合
・受給者証をお持ちの方が島根県に転入される場合
これらの場合については下記リンク先をご覧ください。
10.問い合わせ先一覧
| 保健所名 | 担当課 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 松江保健所 | 医事・難病支援課 |
松江市東津田町1741-3 (いきいきプラザ島根3階) |
0852-23-1315 |
| 雲南保健所 | 総務企画スタッフ | 雲南市木次町里方531-1 | 0854-42-9623 |
| 出雲保健所 | 医事・難病支援課 | 出雲市塩冶町223-1 | 0853-21-1191 |
| 県央保健所 | 医事・難病支援課 | 大田市長久町長久ハ7-1 | 0854-84-9825 |
| 浜田保健所 | 医事・難病支援課 | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5555 |
| 益田保健所 | 医事・難病支援課 | 益田市昭和町13-1 | 0856-31-9548 |
| 隠岐保健所 | 総務医事課 |
隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 (島根県隠岐合同庁舎2階) |
08512-2-9901 |
11.肝炎に関するリンク
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp