島根の職人育成事業
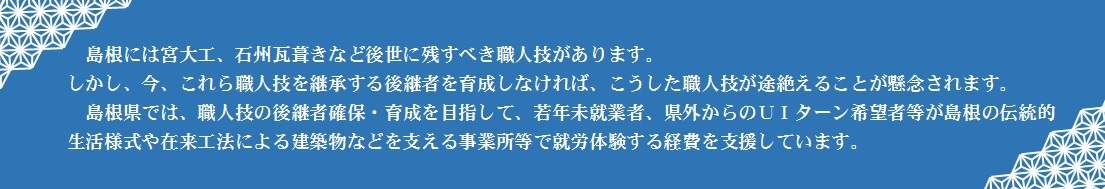
■就労体験受入までの流れ(まずは、島根県技能士会連合会へ連絡!)
1.就労体験を希望者される方は、島根県技能士会連合会へ連絡(TEL:0852-23-1707)
2.連合会が受入先と調整、面接を実施
3.体験者、受入者連名で事業計画書(兼助成申込)を提出
4.連合会、体験者、受入先で確認書を取り交わす
5.連合会から体験者、受入先に決定通知
6.就労体験開始
受入先事業者
受入先事業者、就労体験の内容は変更になる可能性があります。
就労体験を希望される方は、島根県技能士会連合会(TEL:0852-23-1707)までご連絡ください。
(受入先事業者も募集しています。ただし、体験対象職種の技能士会会員事業者に限ります。)
大工・宮大工
建具・組子
造園
和裁
左官
建築板金
受入先事業者の声
体験者の声
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp
