安来市
|
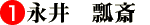 (1881〜1945・安来市出身) (1881〜1945・安来市出身) |
  |
| 新聞人・作家・俳人。執筆担当したコラム「天声人語」は末尾を時事俳句で結び人気を博した。著書に『鎮撫使さんとお加代』『白隠和尚』他多数。 |
|
| 松江市 |
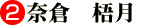 (1876〜1958・松江市出身) (1876〜1958・松江市出身) |
  |
| 正岡子規の日本派の句会「碧雲会」を結成するなど、山陰俳壇の先覚者として活躍。松江市北公園に句碑がある。勝部仇名草編になる「梧月句集」がある。 |
|
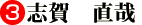 (1883〜1971) (1883〜1971) |
 |

写真提供:白樺文学館 |
| 雑誌『白樺』の創刊に参加。小説の神様とも称された。大正3年、松江市で過ごしたひと夏を『濠端の住まひ』に描く。その他、島根に因む作品は『暗夜行路』等。 |
|
 (1892〜1927) (1892〜1927) |
 |

|
| 『鼻』が夏目漱石の目に留まり、文壇にデビュー。新理知派または新思潮派と呼ばれ、『地獄変』をはじめとする数々の名作を世に送り出した。大正4年、松江市を訪れ『松江印象記』(松陽新報掲載)を記す。 |
|
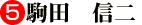 (1914〜1994) (1914〜1994) |
 |
| 作家・中国文学者。昭和21〜30年まで松江市在住。54年に菊池寛賞を受賞。松江市が舞台となった作品は『石の夜』、随筆『湖と私』など。 |
|
鹿島町
(現松江市) |
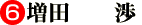 (1903〜1977・鹿島町(現松江市)出身) (1903〜1977・鹿島町(現松江市)出身) |
  |

|
| 中国文学史研究会を結成。著作は『魯迅の印象』他多数。魯迅との師弟愛は中国で評価され戦後の日中国交回復に尽力。鹿島歴史民俗資料館(0852-82-2797)には記念室がある。 |
|
東出雲町
(現松江市)
|
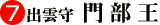 (生年不詳〜745) (生年不詳〜745) |
 |
| 出雲国守にして歌人。出雲守に任ぜられたのは養老5年(721)から天平初年頃(729)、あるいは神亀元年(724)までとされる。東出雲町阿太加夜神社に歌碑がある。 |
|
広瀬町
(現安来市) |
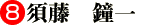 (1886〜1956・広瀬町(現安来市)出身) (1886〜1956・広瀬町(現安来市)出身) |
  |
| 文芸進路社を設立し、「文芸道」を主宰。著書に小説集『痛める花片』『愛憎』『勝敗』『人間哀史』、歌集『故郷』、句集『春待』他多数。 |
|
仁多町
(現奥出雲町) |
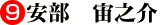 (1904〜1983・仁多町(現奥出雲町)出身) (1904〜1983・仁多町(現奥出雲町)出身) |
  |
| 旧制大社中学校(大社町(現出雲市))教師を経て上京後、詩誌『高踏』『詩研究』等を発行。詩作、詩研究、後輩育成に尽力。著書に『稲妻』『白き頁と影』など。大社中学校に詩碑がある。 |
|
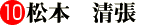 (1909〜1992) (1909〜1992) |
 |

写真提供:文藝春秋 |
| 28回芥川賞受賞後、名実ともに日本文壇の最高峰として数々の名作を発表。島根県を舞台とした作品は『砂の器』『数の風景』『顔』他多数。 |
|
三刀屋町
(現雲南市) |
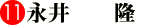 (1908〜1951・三刀屋町(現雲南市)出身) (1908〜1951・三刀屋町(現雲南市)出身) |
  |

|
| 作家、医学博士。代表作に『長崎の鐘』『この子を残して』『乙女峠』他多数。自らも被爆しながら原子医学の研究や原爆傷病者の相談にあたった功績を讃え、永井隆記念館(三刀屋町(現雲南市))が建てられた。 |
|
| 出雲市 |
 (1929〜1993) (1929〜1993) |
 |
| 著作に詩集『我が砦』『不帰順の地』。『葉紀甫漢詩詞集(1.2)』で、新しい言語表現の可能性を開いたとして歴程賞を受賞。 |
|
斐川町
(現出雲市)
|
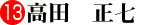 (1913〜1978・斐川町(現出雲市)出身) (1913〜1978・斐川町(現出雲市)出身) |
  |
| 詩誌『二十五年』発行。詩集『風土記』等刊行。出雲の歴史、風土をうたう農民歌人として評価を得た。 |
|
大社町
(現出雲市) |
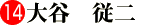 (1915〜1990・大社町(現出雲市)出身) (1915〜1990・大社町(現出雲市)出身) |
  |
| 代表作に長編叙情詩『朽ちゆく花々』。出雲阿国研究の第一人者。 |
|
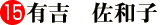 (1931〜1984) (1931〜1984) |
 |
| 社会問題に目を向けた『恍惚の人』『複合汚染』は大ベストセラーとなる。大社町(現出雲市)出身といわれる出雲阿国の半生を描いた『出雲の阿国』は僅かに残された資料と伝説、史実を見事につなぎ合わせた力作である。 |
|
湖陵町
(現出雲市) |
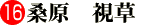 (1908〜1994・湖陵町(現出雲市)出身) (1908〜1994・湖陵町(現出雲市)出身) |
  |

|
| 『出雲俳壇の人々』が俳人協会第2回俳句評論賞受賞。著書に『出雲俳句史』句集『湖畔』『さくら花』等多数。出雲市胎泉寺に句碑がある。 |
|
| 大田市 |
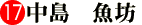 (1725〜1793・大田市出身) (1725〜1793・大田市出身) |
  |
| 芭蕉を慕い、生涯好んで旅をした。魚坊塚(句碑)が出雲市、大田市、仁多町にある。著書に『しのぶ庵詠草』他多数。 |
|
邑智町
(現美郷町) |
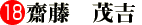 (1882〜1953) (1882〜1953) |
 |

|
| アララギ派の代表歌人。柿本人麻呂終焉の地を探して数度来県。島根県に関する随筆に『手帳の記』『鴨山踏査余録』等多数。邑智町(現美郷町)に齋藤茂吉鴨山記念館がある。 |
|
三隅町
(現浜田市)
|
|
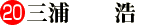 (1930〜1998) (1930〜1998) |
 |
| ザ・ミッシング』で国際政治ミステリーと言う新分野を開拓。父の実家が三隅町のため少年期を浜田市で過ごした。『津和野物語』や『蛇の舞う夜』など石見地方を舞台にした作品も多数発表。 |
|
| 益田市 |
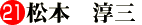 (1894〜1950・益田市出身) (1894〜1950・益田市出身) |
  |
| 詩集『二足獣の歌へる』。わが国初のプロレタリア詩誌『鎖』、雑誌『詩を生む人』『黒嵐時代』等を主宰した。 |
|
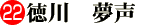 (1894〜1971・益田市出身) (1894〜1971・益田市出身) |
  |

|
| 俳優、漫談家、著述の名手と多彩ぶりをみせた芸能文化人。著書に『夢声戦争日記』、句集『夢諦軒句日誌二十年』他多数。益田市の柿本神社への献句、益田音頭作詞など郷土愛の強い人だった。 |
|
津和野町
|
 (1901〜1971・津和野町出身) (1901〜1971・津和野町出身) |
  |

|
| 『花の宴』で第2回芥川賞候補、『春の鼓笛』で池谷信三郎賞受賞。母親は女優の伊沢蘭奢。代表作『森區鳥外』、『出雲路』、『面影』他多数。 |
|
| 隠 岐 |
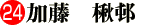 (1905〜1993) (1905〜1993) |
 |

|
| 昭和の芭蕉と呼ばれ、人間探求派の俳人として活躍。昭和16年3月後鳥羽院を訪ねて隠岐に来島。隠岐紀行176句を詠み、紀行文集『隠岐』、句集『雪後の天』に収める。 |
|
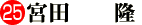 (1913〜1982・海士町出身) (1913〜1982・海士町出身) |
  |
| 放送劇やコント、随筆、シナリオ等も執筆。「玉造小唄」「東京五輪音頭」等多数発表。仁多町(現奥出雲町)玉峰山公園内に句碑がある。 |
|
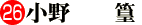 (802〜852) (802〜852) |
 |
| 『古今和歌集』『和漢朗詠集』等に和歌、漢詩が収められている。遣唐副使としての乗船を拒否したため隠岐に流された。2年後に赦された後に従三位まで出世する。 |
|










