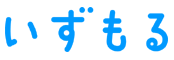島根県立美術館
島根から世界へ一生誕150年石橋和訓展
開催期間:3月6日(金)~6月8日(月)
島根県出身の画家・石橋和訓(1876-1928)は、明治期にイギリスに渡りロンドンのロイヤル・アカデミーで西欧伝統の絵画技法を身につけ、主に肖像画家として国内外で活躍しました。このたびその生誕150年という記念すべき年に初の大規模な回顧展を開催し、世界へと大きく羽ばたいた郷土出身の画家を顕彰します。
国宝松江城
松江歴史館
企画展「連続テレビ小説『ばけばけ』の世界と小泉セツと八雲の時代」
開催期間:12月26日(金)~2026年3月29日(日)
本展では連続テレビ小説「ばけばけ」の放送を機に、ドラマのモデルとなった小泉セツと夫の八雲が生きた明治時代の松江を取り上げます。
ドラマは実際の人物や出来事を参考にしたフィクションであるため、ドラマと比較しながら人物や出来事を歴史資料から紹介します。また、ドラマのセットの再現や衣装と小道具等を展示します。明治時代の松江で実際に起こった出来事を知り、「ばけばけ」の世界の奥深さを体感してください。
スポット展「松江藩家老・乙部家の所蔵品」
開催期間:2月3日(火)~3月29日(日)
江戸時代、現在の松江歴史館の場所には松江藩代々家老大家のひとつである乙部九郎兵衛家の上屋敷がありました。乙部家に伝わった古文書類は、「乙部家文書」として2005年に当館に寄託されています。
乙部家の所蔵品、特に絵画コレクションは、かつて雲州松平家七代藩主・松平治郷(不昧公)の「雲州蔵帳」と並び称されるほど著名でした。収集の中心人物は同家十代の可時(よしとき)です。可時時代の「御道具帳」には、現在国宝や重要文化財に指定される驚くような名品を数多く見出すことができます。
今回は、乙部家旧蔵の伝雪舟筆「真山水図」が当館に寄託されたことを記念し、地元松江で初めてご紹介するものです。乙部家が所蔵品保管に用いた特別な外装「乙部仕立」もあわせてご覧下さい。
ミニ展示「桃の節句のお人形-お雛様と天神様-」
開催期間:2月3日(火)~3月29日(日)
山陰地方では桃の節句に子どもの健やかな成長を願い、女の子のための雛人形と男の子のための天神人形を飾りました。そうした風習に根ざして、松江には天神人形を作る職人やそれを売る人形店があったことも資料により伝わります。本展では、大正時代頃までみられたという、お雛様と天神様を並べて飾る松江の雛祭りを偲びます。
写真展「神々の在す国-小泉八雲とセツのまなざし」
開催期間:2月17日(火)~3月29日(日)
小泉八雲が滞在時に感じ取った情景と精神性を、現代の写真家である古川誠氏によるまなざしを通じて再構成した写真展です。
写真展「神々の在す国-小泉八雲とセツのまなざし」(外部サイト)
出雲キルト美術館
出雲玉作資料館
田部美術館
四季の茶道具「三春に遊ぶ」
開催期間:2月26日(木)~4月26日(日)
梅の花もほころび始めました。下萌えの時季にふさわしい茶道具の数々を展示致します。一足早い春の訪れを美術館でお楽しみ下さい。
モニュメントミュージアム来待ストーン
冬季企画展「小泉八雲と松江の石八雲が惹かれた石の趣き」
開催期間:12月17日(水)~2026年3月29日(日)
松江の地で約1年3ヶ月を過ごした八雲は、島根県尋常中学校と島根県尋常師範学校の英語教師として勤める傍ら、各地の社寺や景勝地を巡るなどして、見聞や交友関係を広げていきました。そして、松江を去った後も、様々な事象、事物、伝承などに関心を示し、日本に関する多くの著作を出版しましたが、その中には「石」にまつわる記述も散見されます。今回の企画展では、小泉八雲が著作において触れている様々な「石」や、松江で暮らしていた当時に巡った先々の「石造物」、「岩石」などを紹介します。
冬季企画展「小泉八雲と松江の石八雲が惹かれた石の趣き」(外部サイト)
安部榮四郎記念館
小泉八雲記念館
小泉セツ-ラフカディオ・ハーンの妻として生きて【第2期】
開催期間:6月13日(金)~2026年9月6日(日)
この秋からNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が放送されることから、延長して開催します。ドラマとともに楽しんでください。
本展では、第1章「セツの生い立ち」、第2章「セツとハーンの物語」、第3章「小泉八雲夫人」という構成の中で、セツ直筆の草稿、帰化に関する書類、ハーンの友人からセツ宛書簡、「思い出の記」草稿、遺愛品などを展示し、西洋人の妻としてたくましくたおやかに時代を生き抜いた一人の女性にフォーカスしていきます。ハーンの再話文学創作における最大の功労者、小泉セツの生涯に光をあてた展示が行われます。
彼女が夫に与えた影響は計り知れないですが、セツというフィルターを通して、作家ラフカディオ・ハーンを見つめなおしてみませんか。
松島彩イラスト展拝啓ヘルン様セツ様
開催期間:12月19日(金)~2026年3月31日(火)
松江出身の俳優松島彩さんは、現在朝ドラ「ばけばけ」のスタッフとしての方言指導を担当する傍ら、敬愛するヘルンとセツをモチーフにドラマのワンシーンを切り取ったイラストを描いています。松島さんの小泉八雲(ヘルン)への想いは熱く、八雲作品の朗読を始め、現在では、セツが初めてヘルンに語った怪談として知られる「鳥取の布団」に着想を得た映画製作を進行中。松島彩さんのイラスト展示を通して、ヘルンとセツ、そして「ばけばけ」のさまざまなシーンに対する想いを、ヘルンとセツに宛てた手紙とともに紹介します。
出雲かんべの里
しまね海洋館アクアス
季節限定新シロイルカパフォーマンス
浜田市世界こども美術館
tuperatuperalaboratoryツペラボ
開催期間:3月7日(土)~5月31日(日)
「ツペラボ」は、絵本や工作など様々な作品を生み出すユニット“tuperatupera”を研究するラボ。
どうやってアイデアが生まれるのか?絵本の原画をみながら発見したり、身近な素材を使った手作り工作をみた後で、実際にユニークな創作にチャレンジすることもできます。最後には、島根県西部に伝わる伝統芸能石見神楽にちなんだ「DJおろちくん」が登場!!大迫力のおろちが生み出す音楽にあわせて、ノリノリダンスで盛り上がること間違いなし☆「ツペラボ」でヒラメキとトキメキをみつけよう!
tuperatuperalaboratoryツペラボ(外部サイト)
浜田市浜田郷土資料館
企画展「郷土ゆかりの絵画・工芸品藤長操コレクション」
石正美術館
企画展「石本正ヨーロッパ美術の旅-中世を夢みて-風景スケッチを中心に」
開催期間:12月6日(土)~2026年3月8日(日)
外国語の画集やガイドブックを手に行先を自ら調べ上げ、約20年の間に9回、最大で3ヶ月という長期間にわたって約30名の教え子たちとともにヨーロッパ中をバスで走った。旅のなかでは常に、見たいものへと我先に駆け寄り美に感動する石本の姿があった。本展では、『ヨーロッパ美術の旅』の道中で描かれた風景スケッチを中心に展覧し、画家の感動の旅の足跡をたどる。
企画展「石本正の視点vol.1朱と白」
開催期間:3月20日(金・祝)~5月24日(日)
情熱や生命力など力強さを感じる色、朱(あか)。静寂や清らかさ、神聖さなどのイメージを持つ白。視覚的にも心象的にも対照的な朱と白は、古くから慶事や神事といった人々の暮らしの様々な場面で使われてきた色の組み合わせです。本展では、このふたつの色に着目して日本画家・石本正(1920-2015/浜田市三隅町出身)の作品をご紹介します。女性の衣服やメイク、花の色や背景など多様に取り入れられた朱と白。色遣いからみえてくる画家の想いや創意工夫をお楽しみください。
島根県立古代出雲歴史博物館
島根県立八雲立つ風土記の丘
企画展「茶臼山西南麓の遺跡群~山代郷正倉とその周辺~」
開催期間:12月24日(水)~2026年3月2日(月)
黄昏の古代、目覚める中世。茶臼山麓が語る、時代の転換点。断片から紐解く、古代のその先。
春季企画展「奇妙なコレクション-大井窯の須恵器たち-」
開催期間:3月18日(水)~6月15日(月)
松江市にある大井窯跡群は、古墳時代から平安時代にかけて出雲全体の須恵器づくりをつかさどっていた一大工場です。須恵器の窯跡では「失敗品」も多く出土します。この展示では多くの「失敗品」をあつめ、須恵器をつくっていた人びとの試行錯誤に迫ります。
春季企画展「奇妙なコレクション-大井窯の須恵器たち-」(外部サイト)
宍道湖自然館ゴビウス
荒神谷博物館
「出雲の原郷」展
開催期間:2月21日(土)~7月5日(日)
弥生時代の青銅器が380点と全国的にみても圧倒的な数が埋納された荒神谷遺跡。1984年の世紀の発見以来、「古代出雲王国」をめぐって多くの説が出されています。常設展では、地形の変化を背景に出雲の風土と人々の営みを、斐川町内からの出土品を中心に紹介します。また、当時の感動をそのままに、青銅器発見の経緯や発掘の様子をまとめたドキュメント映像の上映も行っています。
ホール展「7月28日の出雲の空襲~ふるさとが戦場になった日」
開催期間:2月21日(土)~3月30日(月)
島根で空襲被害が集中した昭和20年7月28日、その日何が起こっていたのか…その痕跡を写真やパネルでわかりやすくご紹介します。また昨年亡くなられた郷土史家で空襲被害に詳しい高塚久司氏の生前の功績を偲びます。
ホール展「7月28日の出雲の空襲~ふるさとが戦場になった日」(外部サイト)
出雲弥生の森博物館
ギャラリー展「日御碕神社と徳川家光・松平治郷」
開催期間:11月26日(水)~2026年3月9日(月)
「日御碕神社の造営と徳川家光」「白糸威鎧の修理と松平治郷」に焦点を当て、当時の有力者たちと、日御碕神社と国宝をめぐる歴史について紹介します。
春季企画展「須佐神社の本殿」
開催期間:2月14日(土)~5月11日(月)
須佐神社(出雲市佐田町)では、「令和の御遷宮」事業として本殿の修理工事が行われ、現在は保存修理を終えた社殿の姿を見ることができます。令和7年7月には、「須佐神社の棟札」45点が新たに出雲市有形文化財に指定されました。棟札とは、工事の日付や職人の名前など、建物の工事にかかわる様々なことがらを記した板のことです。中世から現代にかけて大切に保管されてきた棟札からは、須佐神社をめぐる歴史を読み取ることができます。今回の展示では、「保存修理」と「棟札」の二つの視点から、須佐神社の本殿の歴史についてご紹介します。
出雲文化伝承館
萬祥山焼展
開催期間:3月7日(土)~5月31日(日)
萬祥山焼(ばんしょうざんやき)は、明治5年(1872)頃、日野源左衛門が現出雲市大津町の豊富な粘土を使用して開窯(かいよう)したのが始まりです。はじめは「来原焼」と称し、継いだ伊太郎が日用雑器を製作しました。大正7年(1918)、源左衛門の孫・義長が継承すると、それまでの黄釉系軟陶から民芸風に転換して創作に勤しみ、大正11年に窯名を「萬祥山」と改めました。また昭和15年(1940)には分窯「大社窯」を設置しました。本展では、出雲を代表する伝統工芸品として長く親しまれ、令和5年(2023)に惜しまれながら閉窯(へいよう)した萬祥山焼の変遷をたどるとともに、その優れた作品を紹介します。
平田本陣記念館
特別展「浮世絵美人-百花繚乱お江戸美人のライフスタイル-」
開催期間:3月14日(土)~5月10日(日)
本展は、江戸に生きる女性たちの暮らしや仕事、ファッションやコスメに焦点をあて、豪華絵師たちによって描かれた浮世絵を紹介します。浮世絵は現代のファッション誌さながら、当時のコーディネートや様々な娯楽を今の私たちにも伝えます。江戸の女性たちが何に興味を持ち、何を粋(いき)と感じたのか、現代にも通じる彼女たちの美へのこだわりや人生を愉しむいきいきとした姿をぜひご覧ください。
特別展「浮世絵美人-百花繚乱お江戸美人のライフスタイル-」(外部サイト)
しまね花の郷
出雲民藝館
開館50周年記念特別展「金津滋の図案」
開催期間:10月29日(水)~2026年5月11日(月)
柳宗悦をはじめとする民藝運動の活動家たちが出雲の地を度々訪れ、民藝の思想がこの土地に根づいていった背景には、その思想と地域の文化を結びつけ、土着の美へと昇華させた人々の存在がありました。その一人が、金津滋(かなつ・しげる)です。松江を拠点に、山陰地方で広く活動した金津は、染物、切絵、陶器への絵付といった創作活動をはじめ、工芸品の蒐集、出西窯での指導、茶会「紅雪会」を主宰するなど、多岐にわたる仕事を手がけました。民藝の息づく出雲地方で、創作と実践を通じてその礎を築いた人物でありながら、意外にもその存在は広く知られていません。本展では、金津の出世作ともいえる型染作品『小泉八雲旧居』をはじめとした様々な図案作品を展示します。出雲民藝館の開館50周年という節目の年に、開館当時から展示に携わっていた金津の仕事をあらためてご紹介できることを嬉しく思います。ぜひご高覧ください。
手錢美術館
企画展「お茶のこころ~茶の湯の工芸~」
開催期間:3月4日(水)~5月31日(日)
島根県立石見美術館(島根県芸術文化センターグラントワ内)
企画展「森鴎外ゆかりの洋画家小堀四郎」
開催期間:4月25日(土)~6月15日(月)
本展では、四郎が名声にこだわらず自らの芸術を貫いた人生を振り返り、物事の本質を追求した創造性の高さに着目いたします。その美への純粋な眼差しは、情報化社会で迷いの多い現代を生きる私たちの心を強く揺さぶります。今回は四郎の油彩画約120点のほか、妻杏奴の油彩画や、恩師・長原孝太郎、藤島武二の作品など、小堀四郎の芸術に深い影響を与えた人々の作品もあわせ約240点を紹介いたします。
島根県立三瓶自然館サヒメル
春の企画展「救え!消えゆく生きものたち2026~
~しまねレッドデータブック山野の生きもの編~
開催期間:3月14日(土)~5月24日(日)
「しまねレッドデータブック」は、島根県内で絶滅の危機に瀕している野生動物の保護・保全活動に役立てられるものです。今回の企画展では、「しまねレッドデータブック2026」掲載種全種を一挙紹介!島根県内でどれくらいの生きものがピンチを迎えているのか、その目で確かめに来てください。また、減少する生きものを生息環境別に紹介。身近なところにもいる絶滅危惧種の存在を知ってください。
春の企画展「救え!消えゆく生きものたち2026」(外部サイト)
三瓶小豆原埋没林公園
石見銀山世界遺産センター
「石見銀山遺跡とその文化的景観」世界遺産の概要紹介パネル展in鞆館
開催期間:3月5日(木)~3月31日(火)
「石見銀山遺跡とその文化的景観」の世界遺産としての価値や歴史などのパネルを期間限定で展示します。
「石見銀山遺跡とその文化的景観」世界遺産の概要紹介パネル展in鞆館(外部サイト)
仁摩サンドミュージアム
くもれびビーズ刺繍作家くものおう個展
開催期間:2月28日(土)~6月28日(日)
くものおうさんは、子供が2歳になり心に余裕が生まれた2015年頃から、今迄に挑戦したことがない何かを始めたいと思い立ち、昔プレゼント用にビーズで指輪を作っていた時の材料を使って、ハンドメイド作品を作り始めました。作品は、主に1~3mmほどの小さなシードビーズが渦を巻くように付けながら、カラーサンドや天然石・糸などその時に心惹かれた素材を組み合わせオリジナルの手法で、身につけるだけでなくそれぞれの物語を想像しながら楽しんでいただけたらという思いで制作しています。今回の企画展では約40点を展示します。
温泉津やきものの里
安来市加納美術館
企画展「鈴木禎三展碗の中の小宇宙」
開催期間:1月11日(日)~4月5日(日)
津山市在住の陶芸家鈴木禎三氏は、瀬戸焼・備前焼に学び、国宝『曜変天目』に魅了されたことから、現在は独自の技法でその制作に取り組んでいます。企画展では曜変天目の小宇宙が広がるようなイメージを喚起する作品や備前焼作品を展示します。
足立美術館
冬季特別展「京都の五人」
開催期間:12月1日(月)~2026年2月28日(土)
栖鳳をはじめ、上村松園、菊池契月、橋本関雪、榊原紫峰の、京都で活躍した日本画家の作品をご紹介します。近代の京都画壇を華やかに彩った五人の芸術の魅力に触れていただくとともに、それぞれに異なる画風をお楽しみください。
新館特別展「今を彩る画家たち」
開催期間:11月19日(水)~2026年3月11日(水)
現代の画家たちがそれぞれの視点で追求した美の世界をご紹介します。画面いっぱいに表される、今の日本画の魅力をご覧ください。
春季特別展「日本画ハイライト足立美術館とっておきの名画」
開催期間:3月1日(日)~5月31日(日)
本展では、当館が所蔵する近代日本画家たちの作品の中から、コレクションを代表する名画を一堂に展示します。横山大観や竹内栖鳳、上村松園ら、画壇に確固たる地位を築き、今なお多くの人々に愛される巨匠たちによる特別展です。この機会に、足立美術館のとっておきの名画をご堪能ください。
春季特別展「日本画ハイライト足立美術館とっておきの名画」(外部サイト)
和鋼博物館
今井美術館
「うちの子参観日」ペットの写真募集展2026
展示期間:2026年1月24日(土)~3月8日(日)
毎年恒例の「うちの子」が美術館に展示される企画展!ただただ自慢したい、可愛いうちの子を見てほしい、そんなみなさんの願いが叶う展示会!
応募は簡単♪今井美術館の公式LINEでお友達登録→トーク画面からうちの子の写真と名前などを送るだけ♪
展示室では保護活動についての動画やパネルなど展示し、捨て犬や捨て猫がこれ以上増えないように、小さな命を守るために啓発活動のご案内を予定しています。
奥出雲たたらと刀剣館
鍛練実演
毎月第2日曜日・第4土曜日10時〜11時半・13時〜14時半
定期的に日本刀鍛練実演を公開しています。奥出雲町在住の島根県伝統工芸士小林三兄弟による見事な実演をご覧下さい。
絲原記念館
奥出雲多根自然博物館
瑞穂ハンザケ自然館
津和野町日本遺産センター
木彫り・津和野百景図展
開催期間:1月10日(土)~2月27日(金)
「津和野今昔・百景図」のストーリーが2015年に日本遺産に認定されたことをきっかけに、地元の木彫り愛好者の会「仔ぐまの会」によって、百景図をテーマとした木彫作品の制作が始まりました。作品は毎年5点ずつ増え、現在は36図がそろっています。展示会場では、幕末の津和野藩の美しい自然や人々の暮らし、どこか懐かしい日常の風景を、あたたかみのある木彫作品でお楽しみいただけます。
安野光雅美術館
「物語の絵本」展
開催期間:12月12日(金)~2026年3月11日(水)
・繪本仮名手本忠臣蔵
・物語の街から村へ
・シンデレラ
「本の表紙」展
開催期間:12月12日(金)~2026年3月11日(水)
・安野光雅著作表紙画
・安野光雅の装丁画
島根県などのミュージアムについてもっと知りたい方はこちら
お問い合わせ先
広島事務所
■■ 島根県広島事務所 ■■
〒730-0011 広島県広島市中区基町11-10(合人社広島紙屋町ビル1階)
TEL:082-209-8775 FAX:082-209-8787
E-mail:hiroshima-ofc@pref.shimane.lg.jp